![]()
| 材木町 (ざいもく) |
世帯数 : 161戸 総人口518人 男性254人 女性264人 自治会長 :落合 精一 |
||
| 町由来 | 土地のどちらを見ても材木のある町、材木の中に人家がある。材木と深い関係から材木町。 | ||
| 幸 (さいわい)   入口会長 山本組長 |
○8月29、30日夏祭り | ||
| 町由来 | 「幸」が降る雨のように降り注ぐ町であれと願望をこめてつけられた説。「幸西山」という山が存在したために町名が生まれたともいう。 | ||
| たこ由来 | 凧印は町の頭文字「幸」、幸を願う気持ちを表す。 | ||
| 一丁目 | 世帯数 : 535戸 総人口1280人 男性623人 女性657人 | ||
| 二丁目 | 世帯数 : 653戸 総人口1837人 男性906人 女性931人 | ||
| 三丁目 | 世帯数 : 318戸 総人口839人 男性418人 女性421人 | ||
| 四丁目 | 世帯数 : 581戸 総人口1397人 男性701人 女性696人 | ||
| 五丁目 | 世帯数 : 367戸 総人口920人 男性456人 女性464人 | ||
自治会長 : 入口 忍 町由来 : たこ由来 : |
|||
| 一言 | 平成13年・西暦2001年・21世紀と時代は変わっていきますが,幸組は初子様のための楽しい祭りを行います | ||
| 栄町 (さかえ)  |
世帯数 | 104戸 総人口255人 男性108人 女性147人 | |
| 自治会長 | 中川 和夫 | ||
| 町由来 | 明示15年鴨江小路,大堀新地,白山下の武家屋敷の有った所が合併して出来た町。城下を守る重要な地域。「栄」はこの町が大いに繁栄する事を祈って名付けた | ||
| たこ由来 | 栄町の「サ」祭りの初参加は明治。戦後は昭和22年から参加。白の中の紺色と鮮明にした。 | ||
| 肴町 (さかなまち)  |
世帯数 : 65戸 総人口182人 男性83人 女性99人 自治会長 :岩附 鉄雄 |
||
| 町由来 | 江戸時代魚を商いする店が並んでいたため肴町(魚町)と呼ばれるようになった。 | ||
| たこ由来 | 旭に飛鶴(日鶴)の町の定紋。肴町の氏神の松尾神社に由来する。ご殿屋台あり | ||
| 篠ケ瀬町 (ささがせ) |
世帯数 : 1595戸 総人口4265人 男性2178人 女性2087人 自治会長 :村松 義信 |
||
| 町由来 | 天竜川の支流の瀬であり、そこには笹がうっそうと根を張って茂っていた土地だったので、「笹箇瀬」となずけられた説。天竜川の氾濫による脅威を少しでも防ぐため竹藪がおおかったので「笹箇瀬」と名をつける。 | ||
| 佐藤西南 (さとう)  佐藤中町  |
一丁目 | 世帯数 : 612戸 総人口1678人 男性789人 女性889人 | |
| 二丁目 | 世帯数 : 417戸 総人口1082人 男性528人 女性554人 | ||
| 三丁目 | 世帯数 :218戸 総人口578人 男性285人 女性293人 | ||
| 自治会長 :池谷 久行(西町) 溝口 直樹(南町) 大身 悦男(中町) |
|||
佐藤中町 たこ由来 |
昭和2年和地山公園で初参加。町の頭字変体かな「さ」斜め上下に藤の花,町名が分かれて町の頭文字を変体仮名にしている。ご殿屋台あり | ||
| 佐藤西南町 たこ由来 |
昭和25年和地山公園で初参加。町の頭字に佐藤町の藤を逆さ藤をザイン化。町民全体が丸く仲良く町の発展の願いをこめた。ご殿屋台あり | ||
佐鳴台1丁目 佐鳴台 (さなるだい)  |
一丁目 | 世帯数 : 551戸 総人口1473人 男性728人 女性745人 自治会長 :飯尾 正勝 |
|
| 二丁目 | 世帯数 : 714戸 総人口1774人 男性893人 女性881人 自治会長 :高柳 保 |
||
| 三丁目 | 世帯数 : 1570戸 総人口4124人 男性1971人 女性2153人 自治会長 :伊澤 喜一 村本 三郎(県営団地) |
||
| 四丁目 | 世帯数 : 810戸 総人口2202人 男性1090人 女性1112人 自治会長 :石原 廉太郎 |
||
| 五丁目 | 世帯数 : 518戸 総人口1258人 男性634人 女性624人 自治会長 :二橋 久雄 |
||
| 六丁目 | 世帯数 : 386戸 総人口912人 男性468人 女性444人 自治会長 :鈴木 貞雄 |
||
| 町由来 | 佐鳴湖東岸大地にできた町で名付けられた。佐鳴湖を昔「猿投の浦」と呼称した。 | ||
| たこ由来 | 家康の正室、築山御前鎮魂(般若心経)を念じつつ、女性の喜怒哀楽を表現する般若を使用 | ||
| 佐浜町 (さはま) |
世帯数 : 252戸 総人口1075人 男性517人 女性558人 自治会長 :倉田 治平 |
||
| 町由来 | 佐とは砂を現す字。小さな浜辺の意味からつけられた。 | ||
| 三新町 (さんしん) |
世帯数 : 197戸 総人口675人 男性347人 女性328人 自治会長 :仲田 宗雄 |
||
| 町由来 | 三つの新田に由来萱野新田と欠塚向新田(掛塚)、と中辰新田の三つを総称して三新と称す常に新しくあれの意味を持つ。 | ||
| 参野町 (さんじのちょう)  |
世帯数 : 475戸 総人口1417人 男性698人 女性719人 自治会長 :柬原 芳弘 |
||
| 町由来 | 海神三神を祭祀していた土地なので「三神野」(さんじんの)と呼んだが神を呼び捨ててはいけないと思い神を除外して「三野村」と称す。以後「参野町」となる。 | ||
| たこ由来 | |||
| 三和町 (さんわちょう)  |
世帯数 : 846戸 総人口2443人 男性1246人 女性1197人 自治会長 :美和 陽一朗 町由来 : たこ由来 : |
||
| 塩町 (しおまち)  |
世帯数 | 135戸 総人口260人 男性129人 女性131人 | |
| 自治会長 | 土屋 昌一 | ||
| 町由来 | 塩商人たちが町に住んでいたため「塩町」と呼ばれた。江戸時代この町しか「塩市」が出来なかった。この町に住む商人しか売買ができなかったのは徳川家康のお墨付き特権があるためである。塩以外の商売も数多く生まれ医者の町でもあった。 | ||
| たこ由来 | 町の頭文字「参」背景に斜めの三本線は津毛利,須賀,御手洗神社,の三を表現する。 | ||
| 鹿谷町 (しかたに) 亀山 (かめやま)  |
自治会名 :亀山 世帯数 : 750戸 総人口1690人 男性793人 女性897人 自治会長 :杉石 松一 町由来 : たこ由来 : |
||
| 鹿谷町由来 | 昭和43年亀山,名残、下池川、松城、広沢、上池川、の各町の一部が一緒になって生まれる多くは名残、亀山、この町に「亀井山」という山があったことから「亀山」とつけられた。また、「名残」は諸説があるが、三社神社で姫街道と館山寺街道の分岐、名残を惜しむ姿がよく見られたところから、この地名がつけられた。「亀井山」に鹿谷渓谷や「鹿谷園」と呼ぶ日本庭園があった。ここから「鹿谷」をとる。 | ||
| 亀山たこ由来 | 大正14年新町名として登場、亀の文字に矢をあしらって町印とする、判じ絵である。縁起の良い亀の字に弓矢をヤと読み矢の先端にマを記し町の凧印とする。ご殿屋台あり | ||
| 蜆塚 (しじみつか)  |
一丁目 | 世帯数 : 428戸 総人口1114人 男性525人 女性589人 | |
| 二丁目 | 世帯数 : 672戸 総人口1826人 男性863人 女性963人 | ||
| 三丁目 | 世帯数 : 587戸 総人口1416人 男性740人 女性676人 | ||
| 四丁目 | 世帯数 : 279戸 総人口775人 男性392人 女性383人 | ||
| 自治会長 :須藤 四郎(蜆塚1区) 蜆塚一丁目 上山 一雄(蜆塚2区) 蜆塚二丁目 浅野 登 (蜆塚3区) 蜆塚三丁目 |
|||
| 町由来 | 地名の起源は、蜆の殻を捨てた場所が大きな塚を作っていたところから遺跡の地名ができた。 | ||
| たこ由来 | 町の頭文字「蜆」を取り入れた。ご殿屋台あり | ||
| 十軒町 (じっけんちょう)  |
世帯数 : 659戸 総人口1829人 男性913人 女性916人 自治会長 :本間 昭 |
||
| 町由来 | 島乃郷村の十戸が中心となって荒地を開拓した説。 昔は五人組で隣保を形成、二組の十戸の数字は具合いがよく十軒で村にしたので十軒説。 坂上田麻呂将軍が東征の途地、ここに十軒の宿舎を作る。この日より十軒とよぶ説。 |
||
| たこ由来 | 町の頭文字「十」は発展の情熱を赤字に、背景に斜め三本線これは馬込川を表す。 | ||
| 志都呂町 (しとろ) |
世帯数 : 942戸 総人口2993人 男性1490人 女性1503人 自治会長 :景山 富治夫 |
||
| 町由来 | 南朝と北朝が争う頃、南朝の臣が日本の都にしようと同士が結束。将来の都と将来を志すがミックスしてできた。水はけがよくない土地名「シトロ」の説もある | ||
| 篠原町 (しのはら)  |
世帯数 : 2769戸 総人口9232人 男性4580人 女性4652人 自治会長 :横井 憲一(東) 鈴木 音吉(西) |
||
| 町由来 | 七人の農民の力により開発。平地には「篠」が(竹、雑草、小笹、アシ、シダ等)生えて篠の多い原で多いことで「篠原」が誕生した。 | ||
| たこ由来 | 外枠は太平洋の紺碧の色。内側の丸は参加組合員の心意気を表す。篠原地区の篠を仮名文字「し」として表す。 | ||
| 四本松町 (しほんまつ)  |
世帯数 : 225戸 総人口696人 男性347人 女性349人 自治会長 :大山 英雄 |
||
| 町由来 | 昔、お寺,山の神,権現地区,神社の四ケ所に大きな松がそびえて浜松から見えた説。この土地の守護神として熊野神社を勧請,その神社の境内の各隅に松ノ木を植栽し祀る説。 | ||
| たこ由来 | 町名の頭文字「四」を印とした。 | ||
| 下飯田町 (しもいいだ)  |
世帯数 : 126戸 総人口447人 男性227人 女性220人 自治会長 :石川 元章 |
||
| 町由来 | 江戸時代は上飯田と下飯田とわかれていた。下の飯田は飯田の下にあるから。 | ||
| たこ由来 | 天竜川水域で水を治めるとの発想から、凧印は龍とし、龍の絵柄を印とした。 | ||
| 下池川町 (しもいけがわ)  |
世帯数 : 404戸 総人口1025人 男性484人 女性541人 自治会長 :金原 淳 |
||
| 町由来 | 浜松城の広陵地と牛山間を池川谷。池川が新川となる付近が下池川で集落を下池川町。 | ||
| たこ由来 | 下池川町の古い図柄「イK川」揚がるとKが見にくいため。「イ」を図案化し池川を表現する。ご殿屋台あり | ||
| 下石田町 (しもいしだ)  |
世帯数 : 815戸 総人口2375人 男性1174人 女性1201人 自治会長 :神谷 正信 |
||
| 町由来 | 大洪水の来襲を度々うけ田畑H荒れた、そのため田畑は石だらけいつも石が多い田で石田石が散在する水田の意味から石田で下にあるから「下石田」となった。 | ||
| たこ由来 | 明治時代に消防隊の印に、当時興行をした一座の紋を取り入れデザイン化した「イ菱」を使う。 | ||
| 下江町 (しもえちょう) |
世帯数 : 247戸 総人口731人 男性367人 女性364人 自治会長 :増尾 正孝 |
||
| 町由来 | 芳川村大字江川,下中島,下前島の地区が合併「下江町」と新しく付けた。両下と江川の江を取って下江町となった。 | ||
| 将監町 (しょうげんちょう) |
世帯数 : 428戸 総人口1050人 男性492人 女性558人 自治会長 :坂下 皆明 |
||
| 町由来 | 戦国時代に酒井将監を盟主とする一団がたてこもって遠州一円の僧、宗徒を指導していた。 | ||
| 常光町 (じょうこうちょう) |
世帯数 : 196戸 総人口693人 男性347人 女性346人 自治会長 :名倉 勝平 |
||
| 町由来 | この村は毎年,天竜川の洪水の被害を受けた、そのため農地は荒廃にさらされる事が多い土地の人は「常荒」の村(土地)と呼ぶ。この地に明るい「ひかり」を願い「常光」と書く | ||
| 庄内町 (しょうない) |
世帯数 : 190戸 総人口664人 男性325人 女性339人 自治会長 :田中 泰弘 |
||
| 町由来 | 村櫛荘を開発した豪族が最勝光院へ寄進この地区を庄内の説。新鮮な魚介類がとれるところから「良いところ」という意味からの説。志津城があった、その領内の意味から転じての説。 | ||
| 城北 (じょうほく) 西上池川  東上池川 |
一丁目 | 412戸 総人口969人 男性496人 女性473人 | |
| 二丁目 | 861戸 総人口2095人 男性1048人 女性1047人 | ||
| 三丁目 | 125戸 総人口245人 男性129人 女性116人 | ||
| 自治会名 :東上池川、西上池川 自治会長 :内田 識義(東上池川)城北一丁目〜二丁目、鹿谷、布橋一丁目の一部 中西 則一(西上池川) 西上池川凧揚会 さくら組 MASA'S ROOM http://www.plaza.across.or.jp/~masamiti |
|||
| 城北 町由来 | 上池川町、名残、和地山、追分、中沢、の一部で生まれる。昔からの通称「城北」をつけた。浜松城の北の方面という意味。 | ||
| 上池川町由来 | 浜松城の広陵地と牛山間を池川谷。池川の上流が上池川である。 | ||
| 西上池川 たこ由来 |
昭和18年大きな町を二分、三分に分けた。、戦後復活凧揚げの昭和22年5月初参加。神明宮境内の桜の花びらを使用,花びらの真中に池川の池を抱えた桜花池の図案絵凧。 | ||
| 東上池川 たこ由来 |
戦前は「池」を小さく「川」を太く大きく朱色としていた。戦後は「池」を大きく池川と目立つ印。 | ||
| 庄和町 (しょうわ) |
世帯数 : 318戸 総人口961人 男性478人 女性483人 自治会長 :石塚 正治 |
||
| 町由来 | 昔からの地名庄内村和田を残そうと庄内の庄と和田の和を取って「庄和」 | ||
| 白洲町 (しらす) |
世帯数 : 279戸 総人口1153人 男性551人 女性602人 自治会長 :岡部 清 |
||
| 町由来 | 庄内半島の沖にある中州で、白い砂ばかりの土地だったので「白須」と呼ばれ、年月で白州 | ||
| 白鳥町 (しろとり) |
世帯数 : 218戸 総人口764人 男性380人 女性384人 自治会長 :大石 小三郎(第1) 袴田 義一(第2) |
||
| 町由来 | 坂上田村麻呂将軍がこの土地に陣をい構えた前には泥海と洪水の海があった。将軍が白い潮千珠をこのあれくれる「いわたの海」に投げると水は引き、全て陸地に変わった。この土地には後に白鷺が降りるようになり人々は吉兆とうけとり地名を「白鳥」とした。 | ||
| 白羽町 (しろわ)  |
世帯数 : 1832戸 総人口5270人 男性2637人 女性2633人 自治会長 :村木 (忿)司 |
||
| 町由来 | 遠州灘の白波から名前を付けた説。後醍醐天皇の第二皇子宗良親王が吉野から軍団を引いて東に向かう途中大しけにあった。船は遠州白羽に打ちあげられた。ある朝一本の白羽の矢が松の木にささっった。その方角を見ると宗良親王が通りすぎていくいご白羽の地名がつく | ||
| たこ由来 | 凧印は「白」の字を「羽」で抱きかかえている図柄を町名の由来から取り入れる。 | ||
| 新貝町 (しんがい) |
世帯数 : 226戸 総人口684人 男性334人 女性350人 自治会長 :山田 晴久 |
||
| 町由来 | 蒲神明宮のお神酒を造る場所、お神酒米の田んぼ。新米から加微米(かみまい)という麹を作り麹をもとにお神酒を作った。「かみまい」が転化して「新貝」となった。 | ||
| 新津町 (しんづ)  |
世帯数 : 944戸 総人口2414人 男性1199人 女性1215人 自治会長 :鈴木 元一 |
||
| 町由来 | 「津」は港(湊)を意味しており、かってここに天竜川の川筋に沿った湊があったことからの説刀鍛冶志津三郎兼吉がこの土地に土着したことから「志津」がなまってついたのが定説。 | ||
| たこ由来 | 凧印は町名の頭文字「新」を力強く表す。 | ||
| 新町 (しんまち)  |
世帯数 : 150戸 総人口354人 男性166人 女性188人 自治会長 :藤森 政弘 |
||
| 町由来 | 浜松城下の東の入り口に所在する町、町割その他が近代化された新しい町なので「新町1948年浜松城下町西入り口を「上新町」今の菅原町、東を「下新町」以前は「芽屋町」と呼ぶ芽(かや)ぶき屋根の家が続いていたため。 | ||
| たこ由来 | 米の仲買人が多い「※」の図案を用いていた。「七転び八起」にあやかりだるまの図柄に変更 ご殿屋台あり | ||
| 新都田 (しんみやこだ) |
一丁目 | 世帯数 : 0戸 総人口0人 男性0人 女性0人 |
|
| 二丁目 | 世帯数 : 482戸 総人口1492人 男性765人 女性727人 自治会長 :坪井 晃 |
||
| 三丁目 | 世帯数 : 319戸 総人口996人 男性504人 女性492人 自治会長 :宇津山 勝彦 |
||
| 四丁目 | 世帯数 : 0戸 総人口0人 男性0人 女性0人 | ||
| 五丁目 | 世帯数 : 567戸 総人口1870人 男性949人 女性921人 自治会長 :鈴木 延治 |
||
| 町由来 | 古くは京田郷(みやこだ)「美也古多」の時期もあった。京は、くらの意味「税金」の収納場所物資の集められるところを「都」と呼ぶ。こんなことから名をつけられた。 | ||
| 神明町 (しんめいちょう) |
世帯数 : 18戸 総人口40人 男性15人 女性25人 自治会長 :池野 澄夫 |
||
| 町由来 | 肴町と神明町のボーダーラインの坂の上に天照皇大神を祀る神明宮があった、ということで名前が付けられた。 | ||
| たこ由来 | 町の定紋,現在三組町に鎮座する神明宮が在りし頃使用 | ||
| 砂山町 (すなやま)  |
世帯数 : 928戸 総人口2070人 男性990人 女性1080人 自治会長 :村越 友司(砂山町第一) 加藤 美智雄(砂山町第二) 中西 博雪(砂山町第三) 谷口 悦雄(砂山町第四) 安田 治義(砂山町第五) 増井 庄一(砂山町第六) 砂山町凧揚会 砂組  http://www2c.biglobe.ne.jp/~kinpara/maturi.html http://www2c.biglobe.ne.jp/~kinpara/maturi.html |
||
| 町由来 | 昔、遠州灘や天竜川により作られた砂丘がこのありまであった。この町に住んだ先人の頃見渡せば砂山と松原の姿だったと言われる昔をしのんで「砂山町」を正式な町名にする。 | ||
| たこ由来 | 参加当初は「す」、明治の中頃から新富院のお稲荷さんの狐にあやかり、狐を愛嬌のある図にして町の図柄にした。ご殿屋台あり | ||
砂丘町 |
|||
| 菅原町 (すがわら) |
世帯数 | 314戸 総人口793人 男性375人 女性418人 | |
| 自治会長 | 中村 良一(菅原町東) 増井 正志(西菅原町) |
||
| 町由来 | 明治十五年に浜松宿の西の入り口にあった七軒町と上新町が合併。町名はこの2町の産土神で九州の太宰府天満宮からの祭神の菅原道真公に由来する。 | ||
| 東菅原町 たこ由来 |
元七間町と上新町明治15年合併、梅鉢の定紋は菅原道真公天神様の定紋。現在社は元魚町の松尾神社境内、合併当時の紋章を現在東菅原町が使用ない。東西に凧揚げが二分されてから使用。ご殿屋台あり | ||
| 西菅原町 たこ由来 |
元上新町(堀留)は菅原道真の「菅」文字を使用して参加。ご殿屋台あり | ||
| 助信町 (すけのぶ)  |
世帯数 : 928戸 総人口2070人 男性990人 女性1080人 自治会長 : |
||
| 町由来 | 豊臣秀吉が朱印状の中に地名とともにみえる、伝承としては助信という刀鍛冶がこの地に土着したためとか、助信という武士がここに帰農して開発にあたる。資料的なものはない。 | ||
| たこ由来 | 昭和11年初参加町名の頭文字「助」を使う。ご殿屋台あり | ||
| 頭陀寺町 (ずだじ)  |
世帯数 : 722戸 総人口2048人 男性1051人 女性997人 自治会長 : |
||
| 町由来 | 頭陀寺は衣食住の貪欲を払拭修行寺ここを中心に町が発展そのまま町名となる。 | ||
| たこ由来 | 秀吉の出世ひょうたん印にあやかり初子の幸運と出世を祈り町仮名「ず」配し凧印とする。 | ||
| 住吉 (すみよし)  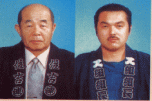 上村会長 菅沼組長 |
住吉会海釣り大会のご案内
● 9月3日(日) 朝 5:30分 NTT前集合 出発
朝 6:30分 出船 みさき貸し船 会費:3000円(船代,弁当,お茶含む)
15時から 住吉会館にて反省会
連絡 幹事 小杉正則 053-471-7567
● 8月26日 住吉会定例会 夜7:30集合 場所: 住吉会館
|
||
| 一丁目 | 世帯数 : 781戸 総人口1765人 男性871人 女性894人 | ||
| 二丁目 | 世帯数 : 629戸 総人口1567人 男性712人 女性855人 | ||
| 三丁目 | 世帯数 : 280戸 総人口676人 男性319人 女性357人 | ||
| 四丁目 | 世帯数 : 368戸 総人口831人 男性421人 女性410人 | ||
| 五丁目 | 世帯数 : 452戸 総人口1203人 男性590人 女性613人 | ||
| 自治会長 :上村 保幸(一丁目〜五丁目の全部) | |||
| 町由来 | 昭和15年12月に住吉町となった。住みよい町を作っていこうと住民の希望を込めて町の名前がつけられ昭和48年住居表示が実施されて住吉となる。 | ||
| たこ由来 | はじめは「す」を採用したが中島諏訪が使用していたので片仮名「ス」にした。ご殿屋台あり | ||
| 一言 | 「初子様の誕生をお祝いする」この基本を忘れずに3日間頑張ります.凧揚げ会場ではガンガン合戦に行きます。宜しく!! | ||
| 西伝寺町 (せいでんじ)  |
世帯数 : 401戸 総人口1114人 男性562人 女性552人 自治会長 :前田 勝志 |
||
| 町由来 | 遠州西部の本山格末寺を三十寺もつ西伝寺がこの土地にあったので命名された。 | ||
| たこ由来 | 凧印は平仮名で町名の頭文字「せ」を表した。 | ||
| 世帯数 : 1165戸 総人口3652人 男性1833人 女性1819人 自治会長 :廣岡 彦雄(橋爪西) 白井 靖弘(橋爪向) 小野 哲靖(吾妻) 高林 照吉(松木) 小野田 金三郎(漆島) |
|||
| (せきし) | 町由来 | 積志講社に由来。村人が明るい住みよい村を目指し、志を同じくする者が集結する。志を積む意味である。 | |
| 早出町 (そうで)  |
世帯数 : 2263戸 総人口6243人 男性3164人 女性3079人 自治会長 :山口 永夫 |
||
| 町由来 | 地名の起源は昔、町一帯は川跡で河原だった。朝、早くから野良に出るから早出村の説。「早出の蔬菜園芸」の特産地だったので早出とよぶ。早出村は田が多い「サデ」の「サ」は田の神様、神のところに早く行こうという意味で。「サデ」が「早出」とよぶ。いずれからの由来 | ||
| たこ由来 | 町名の頭文字「早」を表す。ご殿屋台あり | ||
| 増楽町 (ぞうら) |
世帯数 : 994戸 総人口2610人 男性1341人 女性1269人 自治会長 :藤村 栄一 |
||
| 町由来 | 昔は、叟蘊という。足利将軍が東下りの帰途この地の大きな老松に驚いた。随行していた僧正が一首詠じた。村人はこの松に「於岐奈乃末都(おきなのまつ)」又は「叟蘊の松」後に楽しみを増すほうがよいことから「増楽」に変わった。 | ||
Last updated: 01/03/06♪